
- ソリューション
各国法情報オンラインサービス
Westlaw Japan(日本)
WestlawNext(Westlaw Classic)
Westlaw Asia(アジア)
Westlaw Middle East(アラブ諸国)
Westlaw Japan Academic Suite
Le Doctrinal(フランス)
法的調査ソリューション
Practical Law
Practical Law
Dynamic Tool Set
カスタマーケーススタディ
英文契約書のドラフティングに革新
〈Practical Law〉はスペシャリティを高める教材としても活用できる契約書レビューソリューション
LeCHECK
- サポート
- ECサイト
- イベント情報
- 会社概要
- ログイン
第151回 連邦商標希釈化改正法から5年 ―希釈化に必要な類似性の程度―
TMI総合法律事務所
弁理士 佐藤 俊司
2006年10月の連邦商標希釈化改正法(TDRA=Trademark Dilution Revision Act)からもうすぐ5年が経過する。米国のLaw Schoolに留学していた2006年当時、商標法の前期末試験の問題が試験日の1週間ほど前のニュース※1を題材にして、改正されたばかりのTDRAの当てはめを問う問題だったことを今でもよく覚えている。TDRAは、2003年のVictoria’s Secret事件最高裁判決※2 が1996年の連邦商標希釈化法(FTDA=Federal Trademark Dilution Act)について、「実際の希釈化」が必要と判断したため、「希釈化のおそれ」で足りるとすべく、著名商標権者等の強いロビイングによって改正されたものである。
TDRAでは、「不鮮明化による希釈化(Dilution by blurring)」と「汚染による希釈化(Dilution by tarnishment)」の2つのDilutionの類型が規定されたが、「不鮮明化による希釈化(Dilution by blurring)」について、以下の6つの要素(例示列挙)を考慮すると規定された。
(i) その標章又は商号と著名標章との間での類似性の程度
(ii) その著名標章についての本来的識別力又は使用により獲得された識別力の程度
(iii) その著名標章の所有者が,その標章を実質的に排他的使用をしている範囲
(iv) その著名標章についての認識の程度
(v) その標章又は商号の使用者が,著名商標との連想を想起させる意図があったか否か
(vi) その標章又は商号とその著名商標との間での現実の連想
改正からほぼ5年が経過し、連邦控訴裁判所レベルでの希釈化に関する重要な判断が出てきている。以下、第2巡回区及び第9巡回区連邦控訴裁判所での判決と商標審判抗告部(TTAB)審決から、上記の6つの要素のうちの一つ、「(i)希釈化に必要な類似性の程度」について検討する。
1.第2巡回区連邦控訴裁判所Starbucks事件判決 ※3
| 原告著名商標 (Starbucks Corp) |
被告標章 (Wolfe’s Borough Coffee, Inc) |
|---|---|
 |
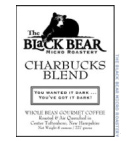 |
第2巡回区における改正前の判例法では、希釈化の有無の判断に際し、ニューヨークの州法やFTDAの下での判例法から取り入れた「very or substantially similar」基準が採用されてきた。一審のニューヨーク南部地区連邦地裁は、STARBUCKSとMR. CHARBUCKSとは、「substantially similar」でないことを理由に希釈化のおそれがないと判断したが、TDRAの文言上は、上記のとおり、「不鮮明化による希釈化(Dilution by blurring)」を判断する際の6つの要素の一つとしての「(i) その標章又は商号と著名標章との間での類似性の程度」が考慮されるとのみ規定されており、「very or substantially similar」であることまでは必要とされていない。
そして、控訴審の第2巡回区控訴裁判所は、TDRAの下では、両標章が「substantially similar」 であることまでは必ずしも要求されないと判示し、一審が「substantially similar」を要求した点において誤りがあるとし、TDRAの文言に沿った判断を行った。
2.第9巡回区連邦控訴裁判所Levi’s事件判決※4
| 原告商標 Levi Strauss’s “Arcuate” design |
被告標章 Abercrombie’s “Ruehl” design |
|---|---|
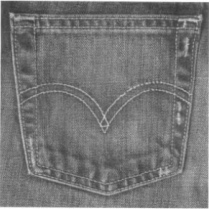 |
 |
一方、第9巡回区における改正前の判例法では、希釈化の有無の判断に際し、「identical or nearly identical」基準が採用されていた。一審の北カリフォルニア地区連邦地裁は、TDRAの「類似性の程度」の解釈についても、この「identical or nearly identical」基準を採用し、両標章が「identical or nearly identical」でない場合には、TDRAの下でも希釈化を主張できないとし、結論として、リーバイスとアバクロの両ステッチは、「identical or nearly identical」でないから、希釈化はないとした。
控訴審においてアバクロは、過去の第9巡回区連邦控訴裁判所の判決に基づき、TDRAの下でも、希釈化の有無を決定する際には、従来の「identical or nearly identical」基準が適用されると主張したが、第9巡回区連邦控訴裁判所は、TDRA以降の第9巡回区連邦控訴裁判所の3つの判決※5を検討したうえで、これらの判決はいずれもTDRAの条文を適切に解釈していなかったとし、過去の第9巡回区連邦控訴裁判所の判例法を拒絶した。
第9巡回区連邦控訴裁判所は、TDRAの文言上、「identical or nearly identical」という文言は出てこないとし、6要素の一つである「類似性の程度」の判断において「identical or nearly identical」であることが決定的な要素となるものではないとし、過去の第9巡回区連邦控訴裁判所で採用されていた「identical or nearly identical」基準は、TDRAの下ではもはや適用されないと判示した。
3.商標審判抗告部Citi Bank事件審決 ※6
| 異議申立人商標(一部) (Citigroup Inc.) |
出願人登録商標(一部) (Capital City Bank Group, Inc) |
|---|---|
 |
 |
希釈化は異議理由にもなることから、TTABにおいても希釈化の有無が争われる場合がある。しかし、通常は2条(d)の混同のおそれの検討がされ、そこで混同のおそれが認められれば希釈化の有無まで検討されることはなく、また、混同のおそれが認められないような場合には、そもそも希釈化が認められるような高い周知性すら有していないことが多いため、TTABで希釈化が問題となる事件はほとんどない。CitiBank事件は希釈化についてTTABが検討した珍しいケースである。
CitiBank事件において、TTABもTDRA下での類似性の程度については、「confusing similarity」以上の「identical or very substantially similar」であることが必要とし、Starbucks事件で第2巡回区控訴裁判所が、「substantially similar」基準を否定した点に言及しつつも、「substantially similar」基準を支持するとして、結論として、両標章は「substantially similar」でないとし、その他の5要素を考慮した上で、Capital City Bank標章は、Citibank標章を希釈化するものではないとした。
なお、異議申立人であるCitibankは米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)にてさらに争ったものの※7、控訴審段階では、希釈化の主張を落とし、混同のおそれの有無に争点を絞って争ったため、CAFCレベルでの希釈化の判断はなされていない。
4.検討
第2巡回区控訴裁判所Starbucks事件判決と第9巡回区控訴裁判所Levi’s事件判決は、共にそれまでの「very or substantially similar」基準や「identical or nearly identical」基準を採用せず、TDRAの文言に従って、「類似性の程度」というよりフレキシブルな基準の下で、希釈化の有無を検討しており、かかる点において同様の方向を示していると言える。かかるTDRAのマルチファクターアプローチの下では、両標章が「very or substantially similar」又は「identical or nearly identical」でなくても希釈化のクレームを主張することができ、、著名商標権者としては、両標章の類似性という一要素の点からは、TDRAをより利用しやすくなったと言えよう。なお、日本での希釈化防止規定である不正競争防止法第2条第1項第2号では、両標章が同一又は類似であることが要件となっている。
両控訴裁判所がTDRAについて同様の方向性を示したことで、今後、他の控訴裁判所でも同様の判決がなされる可能性があり、希釈化の他の争点も含め、今後他の控訴裁判所やCAFCでどのように判断がなされるのかが注目される。
- Evel Knievelという往年のバイクのスタントマンがグラミーアーチスト、Kanye WestのTouch the SkyというVideoに対して、商標権侵害等で提訴したというニュース。なお、事件自体はその後和解により解決。
http://today.msnbc.msn.com/id/16171599
http://www.usatoday.com/life/people/2006-12-12-evel-lawsuit_x.htm - Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003)
- Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. Dec. 3, 2009)
- Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co., No. 09-16322 (9th Cir. Feb. 8, 2011)
- Visa Int’l Serv. Ass’n v. JSL Corp., 95 USPQ2d 1571 (9th Cir. June 28, 2010)
Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628 (9th Cir. 2008)
Perfumebay.com Inc. v. eBay, Inc., 506 F.3d 1165 (9th Cir. 2007) - Citigroup Inc. v. Capital City Bank Group, Inc., 94 USPQ2d 1645 (TTAB 2010)
- Citigroup, Inc. v. Capital City Bank Group, Inc., 98 USPQ2d 1253 (Fed. Cir. 2011)
(掲載日 2011年6月6日)














